
読書評 重症心身障害者の娘と母の記録
うさお
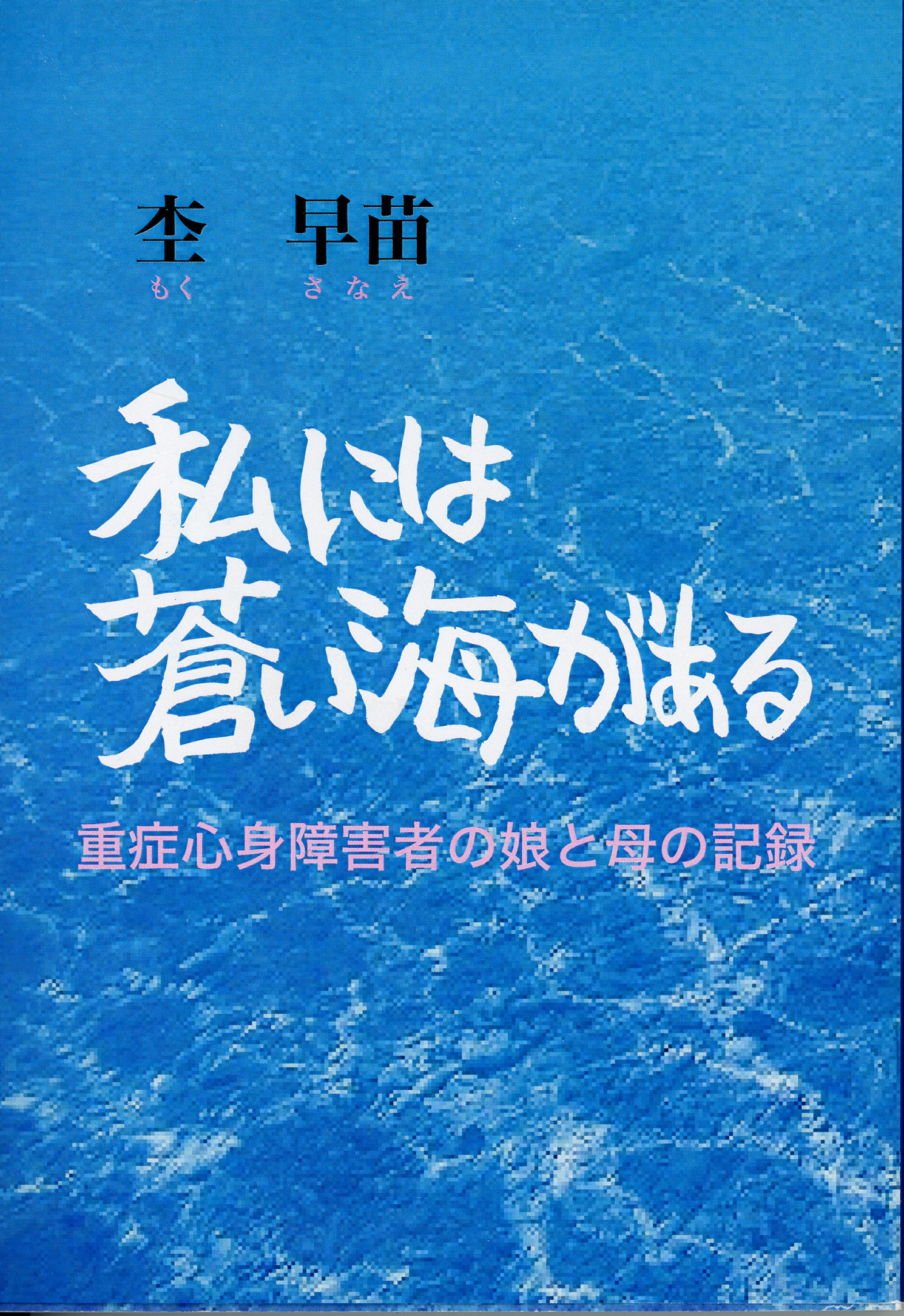
心身障害者の娘さんを持った杢早苗さんの手記が手元にあります。
「私には蒼い海がある―重症心身障害者の娘と母の記録 (1975年) -」
杢早苗 (著) 双葉社 (1975/1/1)
この本を息子さんが自費再販をしました。それを頼み込んで一冊貰いました。
昭和50年に書かれたとはいえ、今の時代で考えると結構壮絶な手記です。(あの頃でもそうだったのかも知れませんが)
幼いころから慕っていた12歳も年の離れた「あんちゃん」と、終戦後に結婚し幸福の絶頂に居ました。男女、2児を授かり貧しい中でも懸命に生きてきます。しかし、心無い義父一家の無遠慮な仕打ちに翻弄されます。
生まれた娘はその成長過程の中で、医師から脳性麻痺だと告げられ、一家は絶望の中に落とされます。が、母は娘を一人の人間として育てることを決意します。
著書の中の言葉、「蒼い海」とは何でしょうか、色々に捉えることが出来ますが、心の中はなかなか推察するのは難しいです。「青い海」ではなく「蒼い海」なのです。
その意味の一つは、心の中の葛藤を表す心象的な言葉かもしれません。症状が好転しない娘に対する心情は、これからのことを考えても決して明るくはありません。心象的にこの色は昏い感じです。
母は家族に相談せず、独断で娘のためにあるだけの金で大島に別荘を買います。娘は温かい気候と広がる海を喜びます。兄の学友たちが大島の別荘に遊びに来ると、一緒に大好きな海遊びをしてくれます。それを心待ちにしている娘がいました。
「蒼い海」のもう一つ意味は、娘に喜びを与える大島の海の色かもしれません。ただ、そこには心身障害者の娘に対する母の気持ちが、「青」ではなく「蒼」だったのかも。
更に別の意味を考えると、娘の症状が緩和する希望があるようにも、または悪化して絶望の深淵を覗く不安があるようにも、「蒼い」色は読めます。
夫も倅もよく娘を介護してくれるのですが、最大の負担はやはり母に掛かってきてしまいます。母は日本心身障害児協会の機関誌「両親の集い」に、定期的に「生きた人形」と題する手記を発表し続けます。
木村美平/西条正晴/杢早苗/他 、日本心身障害児協会内「両親の集い」
重症心身障害者の子供を持つ方への支えになるため、その生活を記録したものです。また、手記を書くことで自分のアイデンティティを保つことも出来たでしょう。
当時の日本は心身障害者の身内をよく思わない風潮がありました。そのなかで、この記録を残すことは身内のことを曝すことにもなり、大きな覚悟のいる行動だったと思われます。
後にM新聞社から取材を受け、母娘のことが広く世間に知られることになります。良かれと思った取材協力でしたが、さらに世間から好奇の目に曝され、彼らを苦しめることになります。
後にこの「生きた人形」の手記は本になります。
「生きた人形」 杢早苗(著) 展望社(1961)
この本は残念ながら今では手に入りません。
うさおが息子さんと親しくなった時に、脳性麻痺の妹がいることを告げられます。戦後の食糧事情が悪い時に、病弱な母が生んだ妹であること。この状況から妹が脳性麻痺に罹っていること。医師からは妹が20歳までしか生きられないと宣告されたこと。
今後も付き合う中で、自分は妹を守る覚悟があることを知って欲しかったのかも知れません。
さて、「私には蒼い海がある」の本では、さらに過酷な記述があります。
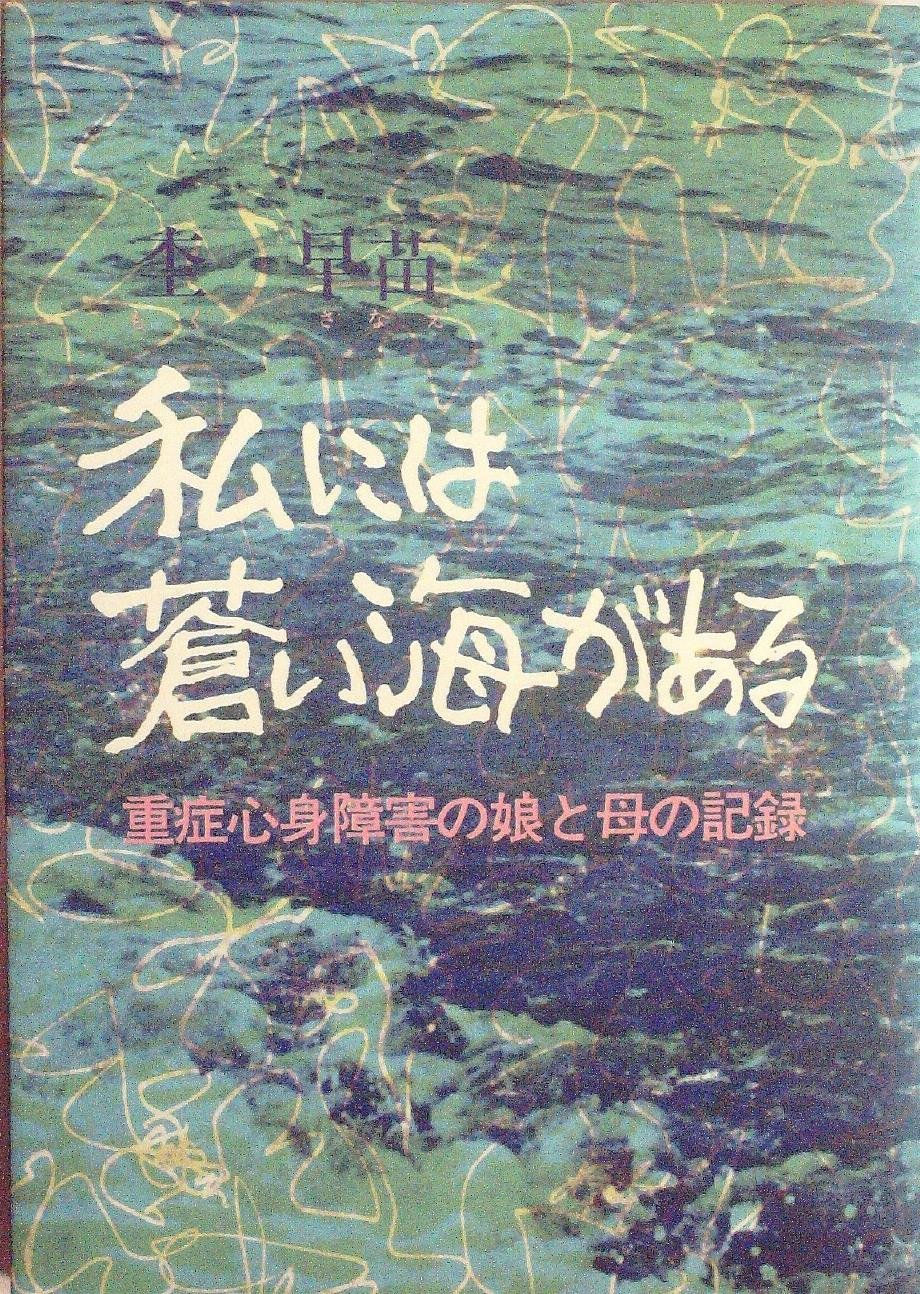 16歳で脳性麻痺の施設に入るには、入居者からの性被害を守るために、子宮摘出手術を受けさせました。父、倅の反対を押し切ってのことです。優生保護法の悪法が生きていた時代です。
16歳で脳性麻痺の施設に入るには、入居者からの性被害を守るために、子宮摘出手術を受けさせました。父、倅の反対を押し切ってのことです。優生保護法の悪法が生きていた時代です。しかし、施設に入ると40㎏の体重が医師たちの得体のしれない注射のお陰で70㎏に増加します。注射を辞めるように頼むと元の体重に戻りました。医師たちの何かの実験にされた可能性があると母は考えています。
その後は、母の献身的な愛情を注がれ、娘は64歳まで生涯を全うすることができました。
ともかく今読むと色々考えさせられる本です。この本が今は一般に売られていないことが残念です。
右の表紙は昭和50年に発行されたときのものです。
浜名湖のリゾートマンションにうさおとCaccoは誘われ、その時に母娘と会いました。娘さんは旅が出来てとても嬉しそうでした。その時を最後に娘さんに会っていません。