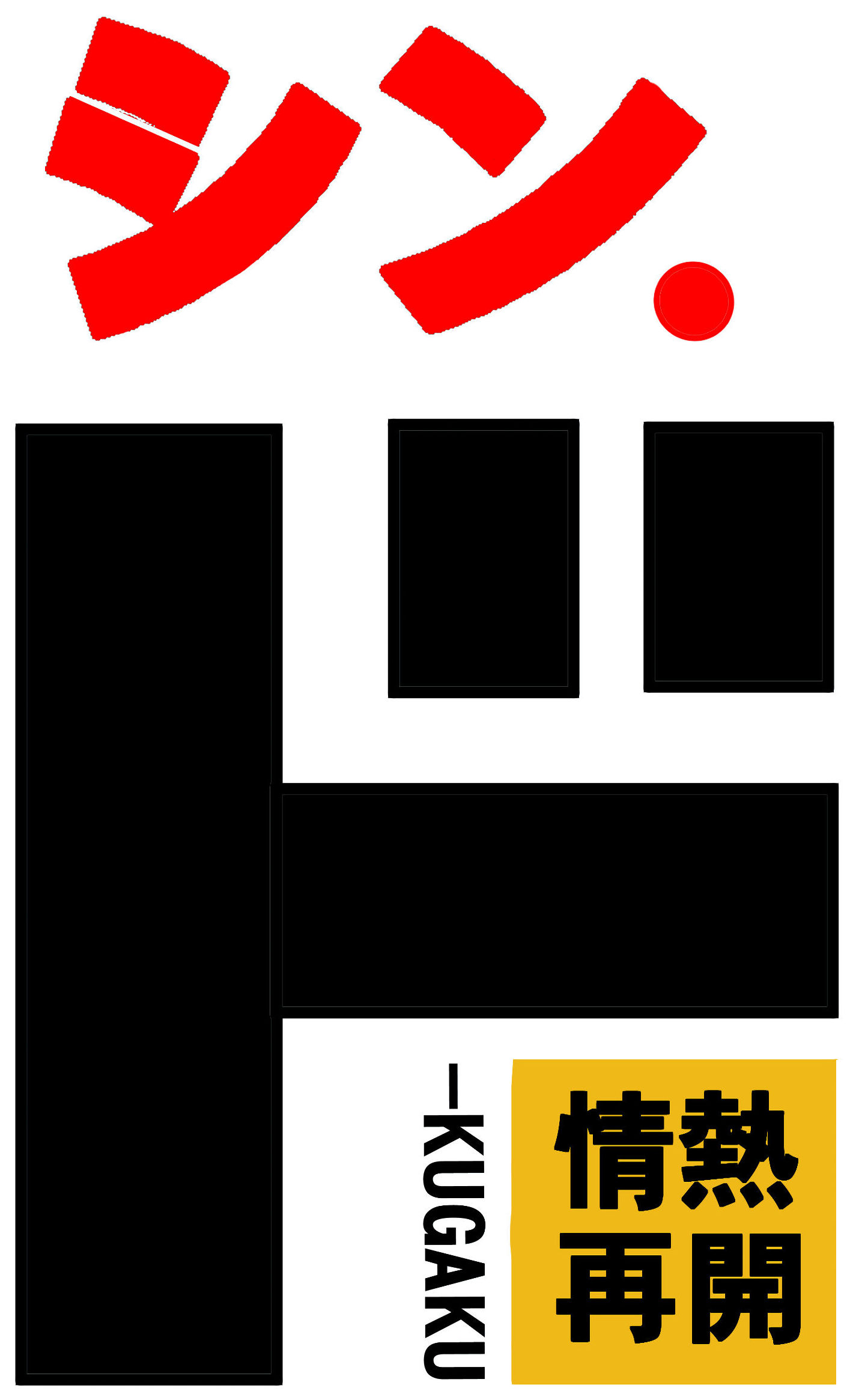


<作成・タツノオトシゴ>
 ベートーヴェンと「荘厳ミサ」(ミサ・ソレムニスOp123ニ長調)、これは古典派に属する作曲家が作り上げた作品として、大変興味のある内容を含んでいます。それは、当時の産業革命という時代背景と、ベートーヴェンという作曲家が、一つの曲を作り上げるまでの苦難のエピソードであり、「ミサ曲」という限られた枠組みの中で作られた曲だからです。
ベートーヴェンと「荘厳ミサ」(ミサ・ソレムニスOp123ニ長調)、これは古典派に属する作曲家が作り上げた作品として、大変興味のある内容を含んでいます。それは、当時の産業革命という時代背景と、ベートーヴェンという作曲家が、一つの曲を作り上げるまでの苦難のエピソードであり、「ミサ曲」という限られた枠組みの中で作られた曲だからです。交響曲第9番(合唱付)Op125ニ短調は、我が国においても多く演奏されてなじみの深い曲ですが、初演は1824年5月7日、ケルントナートーア劇場で行われています。その時に同時に演奏されたのがミサ・ソレムニス(その中からの3曲)という記録からみても、第九とミサ・ソレムニスは同時期に作曲されたペア作品であると言えるのでしょう。
ドイツ生まれのベートーヴェン、ウィーンの暮らしを始めるきっかけとなったのは、「交響曲の父」として有名なハイドンの招きによるものですが、古典派に属する二人の生き方には、大きな違いがあります。モーツアルトやハイドンのように宮廷に雇われた作曲家と違い、ベートーヴェンの場合も、有力なパトロンはいますが、民衆とともに生きる所謂フリーランスだからです。そして、生涯悩まされ続けた「難聴」との闘いにも、その違いが作風にも見て取れるからです。
それでは、ベートーヴェンの生い立ちから見ていくことにしましょう。
彼は1770年の12月16日にドイツ(当時の神聖ローマ帝国)のボンで生まれています。祖父のルートヴィヒ(同名)はケルンで宮廷楽長をしていました。
さらに、父のヨハン・ヴァン・ベートーヴェンは宮廷に仕えるテノール歌手でしたが、アルコール依存症があり人格的に問題があったため、裕福とはいえない一家の精神的な支えは母のマリア・マグダレーナでした。ベートーヴェンは4歳の時から父にピアノを教えられ、6歳(1776年)の時にはケルンで演奏会を開きましたが、正式な音楽教育はこの11歳当時から受けるという状態でした。他の大作家と同じように、ベートーヴェンの才能の開花は早かったのですが、14歳頃からの彼はオルガン奏者として家計を助けてもいます。そして16歳の時(1786年)にモーツァルトの教えを受けています。ベートーヴェンは、モーツァルトを尊敬していて、面会の機会を得た時に弟子入り志願をしていたのは有名な話です。ベートーヴェンもモーツァルトも音楽家の父による薫陶を受け、少年演奏家としてデビューしたという共通の過去を持っているからです。17歳(1787年)で母親を亡くし、一家を支えて働くベートーヴェン、このような家庭環境が彼の性格を気難しくしたという説にも頷けます。1791年12月にはモーツアルトが35歳の若さで亡くなっています。翌年、ベートーヴェンは22歳(1792年)の時にハイドンに弟子入りし、ウィーンを拠点に生活を始めますが、実際にはハイドンの手ほどきを受ける機会は少なかったようです。
 ベートーヴェンが師事した時期は、ハイドンにとっても重要な時期(第1期ザロモン交響曲、全6曲など)で、イギリスへの演奏旅行や代表曲の制作を精力的に行っていたからです。ベートーヴェンは、その年に父親を亡くしています。25歳(1795年)で演奏家としてデビューしていますが、翌年(1796年)にプラハ、ドレスデン、ライプチッヒ、ベルリンなどを半年かけて廻るという大旅行をし、音楽的にも認められはじめ順調な時期でした。ウィーンでの彼は、貴族社会に多くのパトロン、金銭的な支援者を見出すという、抜きん出た才能をいかんなく発揮しますが、その背景には「モーツアルトのような死に方はしたくない!」という考えや、「ハイドンの弟子にはなったが、学んだことは何もなかった」という皮肉な関係もあったのでしょう。ベートーヴェンの肖像画で有名なのは、シュティーラー画による学校などでよく見かけるものですが、手に持つ楽譜の表紙には、ミサ・ソレムニス・ニ長調(D#)と書かれています。
ベートーヴェンが師事した時期は、ハイドンにとっても重要な時期(第1期ザロモン交響曲、全6曲など)で、イギリスへの演奏旅行や代表曲の制作を精力的に行っていたからです。ベートーヴェンは、その年に父親を亡くしています。25歳(1795年)で演奏家としてデビューしていますが、翌年(1796年)にプラハ、ドレスデン、ライプチッヒ、ベルリンなどを半年かけて廻るという大旅行をし、音楽的にも認められはじめ順調な時期でした。ウィーンでの彼は、貴族社会に多くのパトロン、金銭的な支援者を見出すという、抜きん出た才能をいかんなく発揮しますが、その背景には「モーツアルトのような死に方はしたくない!」という考えや、「ハイドンの弟子にはなったが、学んだことは何もなかった」という皮肉な関係もあったのでしょう。ベートーヴェンの肖像画で有名なのは、シュティーラー画による学校などでよく見かけるものですが、手に持つ楽譜の表紙には、ミサ・ソレムニス・ニ長調(D#)と書かれています。 ベートーヴェンの耳の病(混合性難聴と思われる)は28歳頃(1798年)から彼に重い陰を落とし、しだいに深刻化していきました。このような悩みの中で作られたという作品が初期を代表するピアノ・ソナタ「悲愴」(1799年)なのです。その後、31歳(1801年)の時、ピアノを教えていた伯爵令嬢(ジュリエッタ・グイチアルディ)に捧げたピアノ・ソナタ「月光」が完成しており、ピアノ演奏家としての活動は、ベートーヴェンが手がけた多くのピアノ曲からも分かります。
作曲家としても、演奏家としても高い評価を受けた時期に、音楽家にとっては重度の難聴は、想像を絶する苦難であり、医師の診断に疑問を持った ベートーヴェンは弟のヨハン(調剤師)から入手した様々な薬剤を大量に服用していたことが分かっています。
ベートーヴェンの作品では、ピアノが主役を担っているのは138曲中65曲と圧倒的な割合を占めています。ベートーヴェンはモーツァルトと14歳しか違いませんが、モーツァルトよりもずっと多くのピアノに触れていることが見て取れます。
当時作曲家は自分で演奏もするスタイルが一般的で、一流の演奏家であることが必須条件でした。ピアノという楽器が進化を遂げていく過程で、ベートーヴェンは多くの種類のピアノを提供されていたことからも、優れた演奏家であったことが分かります。ピアノの演奏に関して、彼の若い頃の弟子であったリース(ベートーヴェンに師事したのは16歳から20歳(1801?1805年)という青春の時期)の記録から、面白い記述を見つけました。その中で、「ベートーヴェンはピアノにレガートによる音の保持を求め、より大きな音量によるダイナミックな表現を求めたように思います」
さらに「パッセージを弾きそこなったり、際立たせたい音符や跳躍をミスタッチしても、ベートーヴェンはほとんど何もいわなかった。しかしクレッシェンドなどの表現や作品の性格づけに関して足りないところがあると、彼は激怒した。前者はただの事故だが、後者は知識や感性、注意深さを怠っているからこそ起きる??そう彼は言った。実際のところ彼自身も、公開演奏のときに前者のミスはよくやらかしていた」とあります。
まさにベートーヴェンの作風そのものを表していますが、それがピアノとの関係性から生まれたものだとすれば、彼の耳の病(難聴)も作風に影響していると考えられます。
 ベートーヴェンが最初に好みを表明しているのは、ヴァルターのピアノです。
ベートーヴェンが最初に好みを表明しているのは、ヴァルターのピアノです。製作者たちから無償で楽器の寄贈を受けられる立場にあったベートーヴェンが、ヴァルターに対しては代金を支払ってもよいとさえ言っています。
そして、シュトライヒャーのピアノがベートーヴェンに作曲の意欲を起こさせたのです。シュトライヒャーとは親しい付き合いだったこともあり、たびたび手紙で要望を出しています。ある意味、シュトライヒャーのピアノはベートーヴェンとの共同開発だったのではないでしょうか。作曲家は楽器に触発され、楽器の能力を最大限に用いて曲を作り、製作者は要望に応えるべく毎回工夫を凝らして楽器を作る、そのような切磋琢磨し合う関係がピアノを発展させていったと言えるでしょう。このピアノには新たに、難聴だったベートーヴェンのために特別に作られた、金属の箱型の枠が取り付けられています。これは、ピアノの音を聞こえやすくするためのスピーカーの役割を果たすもので、補聴器などの展示と共に、ベートーヴェンの作曲への取り組みをうかがい知ることができます。丁度ピアノという楽器が、産業革命後大きく進化していった時期と重なっており、ベートーヴェンが手掛けた曲と比べてみるのも面白いと思います。
 音が聴こえなくなったベートーヴェンが愛したものに、メトロノームがあります。難聴者は音が聴こえなくても振動と言う形で音を感じることが出来ますが、ベートーヴェンのようにオーケストラを指揮する場合、打楽器の振動は他の楽器の振動で打ち消されてしまうことがあります。そんなベートーヴェンの前に現れたのが1816年にヨハン・ネポムク・メルツェルによって発明されたメトロノームです。曲のテンポが視覚的に把握できるメトロノームはうってつけの道具であり、ベートーヴェンは直ちにヨハン・ネポムク・メルツェルとの親交を持ちます。メトロノームを自分の作曲活動に活用し、1816年以降に作曲されたベートーヴェンの楽曲にはメトロノームの速さが指定されているのです。後にメルツェルはベートーヴェンの補聴器も作っています。
音が聴こえなくなったベートーヴェンが愛したものに、メトロノームがあります。難聴者は音が聴こえなくても振動と言う形で音を感じることが出来ますが、ベートーヴェンのようにオーケストラを指揮する場合、打楽器の振動は他の楽器の振動で打ち消されてしまうことがあります。そんなベートーヴェンの前に現れたのが1816年にヨハン・ネポムク・メルツェルによって発明されたメトロノームです。曲のテンポが視覚的に把握できるメトロノームはうってつけの道具であり、ベートーヴェンは直ちにヨハン・ネポムク・メルツェルとの親交を持ちます。メトロノームを自分の作曲活動に活用し、1816年以降に作曲されたベートーヴェンの楽曲にはメトロノームの速さが指定されているのです。後にメルツェルはベートーヴェンの補聴器も作っています。ドイツの作曲家として有名なベートーヴェンですが、実際の活動の大半(22歳~35年間)は、オーストリアのウィーンで暮らしています。
その間、約70回も住む場所を変えているので、観光の対象となる建物が多く残されている理由が分かります。その引っ越しの多さは、色々と理由がありそうですが、日本でも葛飾北斎はひっきりなしに住まいを変えています。人づきあいが苦手で、片付ける暇がなかったとも言われていますが、仕事を始めると、なりふり構わぬところが二人の共通点なのかもしれません。
 それでは、「荘厳ミサ」、曲の構成についてみていきます。
それでは、「荘厳ミサ」、曲の構成についてみていきます。曲は「キリエ」「グローリア」「クレド」「サンクトゥス」「アニュス・デイ」という伝統的なミサ曲の通常文を構成する5つの部分から成っています。歌詩もラテン語で歌われますが、全体的には純粋な宗教曲というよりは、演奏会的な雰囲気と教会的な雰囲気とをあわせ持ったスケールの大きさがあります。各楽章はかなり長く、初演も全曲ではなく一部だけが演奏されています。
全曲が初演されたのは、意外なことにサンクト・ペテルブルクです。作品はベートーヴェンの生涯のパトロンだったルドルフ大公がモラヴィアのオロモウツの大司教に就任したお祝いとして献呈されていますが、作曲に熱を入れすぎて、就任式には間に合わなかったと言われています。
第1曲キリエの冒頭には「心より出、そして再び心にかえらん」と書かれていますが、ベートーヴェンの作曲技法のみならず、彼の理想や哲学の総決算ともいえる作品です。どことなくフランス革命やナポレオン戦争時代直後の気分が漂うのもベートーヴェンらしいところで、当初はオラトリオで演奏することも考えていたようです。
●第1曲 キリエ :アッサイ・ソステヌート「敬虔に」
ニ長調の和音が鳴った後、静かな前奏が続きます。合唱が「キーリエ」と歌い始めると主部が始まります。この曲は3部構成となっていますが、これはキリエの歌詞に対応しています。テノール、ソプラノ、アルトの順に独唱が出てきます。中間部は、テンポも拍子も変わりロ短調になります。「キリスト、憐れみたまえ」と独唱が歌います。フーガのように展開された後,第1部が再現しますが、ここではより密度の高いものになっています。
●第2曲 グローリア :全体は4つの部分に分かれています。
第1部 アレグロ・ヴィヴァーチェ
オーケストラの強奏に続き、合唱アルトが「グローリア」(いと高き天においては、神に栄光あれ)と高らかに輝かしく歌い始め、ニ長調という輝かしい調性が生きています。「地上には平安あれ」といった歌詞の部分になると、それに対応するかのように穏やかなメロディになります。この対比が聞き所で、後半はテノール独唱も加わって盛り上がり、グローリアの主題が再現します。
第2部 ラルゲット
「世の罪をのぞきたもう御者、われらを憐れみたまえ」という部分です。ため息をつくように、重苦しい雰囲気になります。
第3部 アレグロ・マエストーソ
鋭い分散和音に続き、合唱テノールが「御身は,唯一の聖なる御者」という歌詞を強く歌います。
第4部 アレグロ・マ・ノン・トロッポ・エ・ベン・マルカート
大フーガです。合唱バスと低音楽器が「神なる御父の光栄において。アーメン」というフーガの主題をユニゾンで出します。非常に緊迫感のある展開が続き、「アーメン」という言葉に向かって、壮大なクライマックスを築きあげます。最後にグローリアの主題が再現し、さらに高潮し、アーメン終止で楽章を閉じます。
●第3曲 クレド :この楽章も4つの部分に分かれます。
 第1部 アレグロ・マ・ノン・トロッポ
第1部 アレグロ・マ・ノン・トロッポ合唱バスが「クレード、クレード」と力強く歌い始めます。その後、突如ppに静まり「世々の前に」とつぶやくように歌います。クレド主題による展開が続いた後、「彼は、われら人間のために、天から下りたもう」という内容を表すかのように跳躍のあるメロディが合唱で歌われます。
第2部 アダージョ。ドリア旋法的
合唱テノールが、「精霊によって、マリアより生まれ」と歌い、独唱に継がれていきます。精霊を表すようなフルートの音形など、この辺の描写はとても工夫されています。「十字架につけられ」という歌詞が出てくると、ニ短調のアダージョ・エスプレッシーヴォとなり、苦難に満ちたような雰囲気になります。「3日目によみがえり」という歌詞がア・カペラの合唱テノールに出てくると、気分が変わり、第3部に続きます。
第3部 アレグロ・モルト
「天に昇り」という歌詞を表すように跳躍のある上向の音階で始まります。ここでは最後の審判を表すトロンボーンの音も効果的です。キリストを賛美するような雰囲気が続いた後、クレド主題が再現します。合唱が「アーメン」という言葉でクライマックスを作った後、第4部に入ります。
第4部 アレグレット・マ・ノン・トロッポ
合唱ソプラノが主題、合唱テノールが対主題を静かに提示して、フーガが始まります。オーケストラは、合唱とユニゾンで進んでいきます。ここでも「アーメン」が出ると、テンポが変わり、展開していきます。テンポが遅くなり、独唱が「アーメン」と歌うと、天上に消え入るような感じで楽章を閉じます。
●第4曲 サンクトゥス アダージョ
「聖なるかな万軍の神なる主」という歌詞が独唱によって静かに唱えられます。突如、アレグロ・ペザンテに変わり、壮麗なフガートが展開されます。「ホザンナ、ホザンナ」という歌詞になってと、テンポはさらにプレストに上がります。
続いて、「ベネディクトゥス」に入りますが、その前に前奏曲が置かれています。非常に神秘的な音楽です。コンサート・マスターのヴァイオリン・ソロで高い音を弾き始めると、ベネディクトゥスになります。 このヴァイオリンの音が2本のフルートとともに、3オクターブに渡って下降していきます。この後もソリスト並みに美しいメロディがオブリガートになって延々と続きます。
合唱バスが「ベネディクトゥス」と静かに歌いはじめます。続いて独唱アルトから他の声部へと受け継がれて行きます。途中、合唱が「ホザンナ」と力強く盛り上がりますが、全体に清澄な気分にあふれた楽章です。
前にも述べたように、ケルントナートーア劇場での初演では、第3章の「クレド」と第4章の「サンクトゥス」は省かれて演奏されています。ベートーヴェンのこの曲に対する熱い思いが伝わってくるのではないでしょうか。
●第5曲 アニュス・デイ :全体は3部に分かれます。
第1部 アダージョ
 「アーニュス、アニュス、デイ」と切々とした祈りが始まります。バス独唱のしみじみとした歌が大きな聞き所となります。続いて「ミゼレーレ」という言葉が出て来て、男声合唱~アルトとテノールの二重唱が歌い継いで行きます。最後に四重唱と合唱によって「アニュス・デイ」と繰り返されます。その後、曲が明るいムードに変わり、第2部に入っていきます。
「アーニュス、アニュス、デイ」と切々とした祈りが始まります。バス独唱のしみじみとした歌が大きな聞き所となります。続いて「ミゼレーレ」という言葉が出て来て、男声合唱~アルトとテノールの二重唱が歌い継いで行きます。最後に四重唱と合唱によって「アニュス・デイ」と繰り返されます。その後、曲が明るいムードに変わり、第2部に入っていきます。第2部 アレグレット・ヴィヴァーチェ
暗さのどん底のような状態の後、曲のテンポが軽さを持った調子に転換します。この暗から明への転換はベートーヴェンらしいところです。ベートーヴェンは、ここで「内面と外面のこころの安らぎへの願い」と楽譜に書いています。まず、合唱アルトとバスが「われらに平和を与えたまえ」と歌います。次に合唱ソプラノとバスによって2重フーガ主題が「pacem(平和)」という言葉のもとに展開されます。弦楽器によるピツィカートの上昇旋律が平和への期待感を感じさせてくれます。
中間部はアレグロ・アッサイとなり、不穏な雰囲気になります。ティンパニの弱音の後、トランペットが出て来て行進曲風になります。独唱アルトとテノールが不安げにレチタティーヴォを歌います。その後、最初の部分に戻り、最初より充実した形で「われらに平和を」と歌われます。
第3部 プレスト
トリルを伴う短い主題と第2部に出てきた2重フーガのソプラノの主題とが競うように出てきます。金管楽器とティンパニが終曲の開始を告げ、合唱が「アニュスデイ」と歌い、次に独唱者たちが「dona nobis pacem(我らに平和を与えたまえ)」と歌います。2重フーガのソプラノの主題を回想しながら、盛り上がって行きます。最後はティンパニが神秘的なリズムを打った後、合唱が「pacem」と歌って、全曲が感動的に結ばれます。
(参考文献)名曲解説ライブラリー3.ベートーヴェン.音楽之友社.1992(2003/12/03)
長い時間を掛けて作曲した「荘厳ミサ」、ベートーヴェンはどんな思いを抱いていたのでしょう。
彼は後年、「私の 最高傑作」、「精神の最も実り豊かな所産」と自負したほどであり、出版社への売値は「第九」が600フローリンであるのに対して「荘厳ミサ曲」が1,000フローリンであったことからも、ベートーヴェン自身がこの作品に並々ならぬ自信を持っていたことがうかがえます。
ベートーヴェンが作曲したミサ曲が他にも1曲「ミサ曲ハ長調」作品番号86が有りますが、彼の他の作品集と比べて考えてみると宗教曲や声楽作品が意外と少ないということに気付きます。
後世における曲の評価も分かれていますが、他にも何か特別な理由がありそうな気がします。
初期のベートーヴェンの作品では、22歳(1792年)の時に作曲した「皇帝ヨーゼフ2世の死を悼むカンタータ」があります。ロンドン滞在からボンに立ち寄ったハイドンが、宮廷楽団の演奏で、彼のこの曲を聞き、その才能を認めウィーンへの留学を進めたのです。
モーツァルトが35歳の若さで亡くならなければ、このような展開にはならなかったのでしょう。
 ベートーヴェンの耳の病(混合性難聴と思われる)は28歳頃(1798年)から彼に重い陰を落とし、音楽家として聴力を失うという絶望感から、あの有名な書簡(ハイリゲンシュタットの遺書)が32歳(1802年)に書かれています。
ベートーヴェンの耳の病(混合性難聴と思われる)は28歳頃(1798年)から彼に重い陰を落とし、音楽家として聴力を失うという絶望感から、あの有名な書簡(ハイリゲンシュタットの遺書)が32歳(1802年)に書かれています。自らの難聴による孤独や、それに伴う自殺願望について、弟のカールとヨハンに宛てて書かれています。この手紙は実際には投函されず、私物の中に眠っており、発見されたのはベートーヴェンの死後でした。当時すでに若手の演奏家・作曲家してとして有名になりつつあったベートーヴェンは、「私は人より優れた耳を持っていると人から思われているのに、『すみませんが、耳が聞こえづらいので大きい声で言ってください』などとは恥ずかしくて言えなかった」という生々しい感情を吐露しています。
更に自ら社交場から遠ざかる孤独感や、素行の悪い弟たちに対する複雑な愛情が綴られますが、筆を進めるうちに一転して「それでも私を死から引き止めているのは芸術である」と音楽に対する情熱を自覚し、彼は死を選択することではなく、強い決意へと遺書の内容は変わっていきます。
自らの音楽活動に使命感を感じていたベートーヴェンは「もし後世に自分が不幸だ、と思う者がいて、過去に耳の不自由な音楽家が仕事を完遂したと知ったら、その人たちに生きる勇気を与えることができるのではないか」という内容を綴っています。
自分は芸術家であり、それを成し遂げるまではやはり死ぬことはできない・・・と考え、その後の作品群のように大きく花開くための、決意の書簡であったのではないがと思われます。
 ハイリゲンシュタットの遺書の書かれた前年1801年、ハイドンとの関係を調べていると、晩年のミサ曲、『天地創造ミサ』やオラトリオ『四季』の作品が見当たります。前にベートーヴェンはピアノ作品が多いと述べましたが、宗教曲や声楽曲というジャンル(『合唱』や『荘厳ミサ』などの声楽作品)が意外と少なく、初期の作品はほとんど見当たりません。中期以降、1804年に書かれたオラトリオ「オリーブ山上のキリスト」作品番号85や、その後ベートーヴェンが37歳の創成期に書いた「ミサ曲ハ長調」作品番号86等が中期の作品です。作品番号85は何度かの演奏会で好評を得た記録がありますが、現在ではあまり演奏されておらず、声楽の部分に課題があると云う評価が残っています。『ミサ曲ハ長調』(1807年9月頃)は、キリエ、グローリア、クレド、サンクトゥス、アニュスデイからなり、エステルハージ侯爵(ヨゼフ・ハイドンのパトロン)夫人のために書かれたものです。今までの慣習で、ハイドンは依頼主の夫人のために何度もミサ曲を献上していますが、高齢となったハイドン(1809年5月に死去)は1802年のハルモニーミサ以降は作曲していません。
ハイリゲンシュタットの遺書の書かれた前年1801年、ハイドンとの関係を調べていると、晩年のミサ曲、『天地創造ミサ』やオラトリオ『四季』の作品が見当たります。前にベートーヴェンはピアノ作品が多いと述べましたが、宗教曲や声楽曲というジャンル(『合唱』や『荘厳ミサ』などの声楽作品)が意外と少なく、初期の作品はほとんど見当たりません。中期以降、1804年に書かれたオラトリオ「オリーブ山上のキリスト」作品番号85や、その後ベートーヴェンが37歳の創成期に書いた「ミサ曲ハ長調」作品番号86等が中期の作品です。作品番号85は何度かの演奏会で好評を得た記録がありますが、現在ではあまり演奏されておらず、声楽の部分に課題があると云う評価が残っています。『ミサ曲ハ長調』(1807年9月頃)は、キリエ、グローリア、クレド、サンクトゥス、アニュスデイからなり、エステルハージ侯爵(ヨゼフ・ハイドンのパトロン)夫人のために書かれたものです。今までの慣習で、ハイドンは依頼主の夫人のために何度もミサ曲を献上していますが、高齢となったハイドン(1809年5月に死去)は1802年のハルモニーミサ以降は作曲していません。そのため、自分の後継者としてベートーヴェンの才能を高く評価し、ミサ曲の献上者として推薦しているのです。ベートーヴェンはエステルハージ公に宛てた書簡にて次のように告白しています。「陛下は偉大なるハイドン氏が演奏された無類の傑作をお手元に置き慣れ親しんでおられます故、私は大変慄きつつミサ曲をお渡しすることになります旨、申し上げます。」
ベートーヴェンはハイドンのミサ曲を賞賛して「無類の傑作」と呼んでいます。委嘱主がエステルハージ家という事実は別として、「グローリア」のスケッチから見てとれるように、彼が自作の作曲中にハイドンのミサ曲を研究していたことは明らかです。
 しかし、その結果はハイドンの思惑とは異なり、依頼主(エステルハージ侯爵)はこの作品を公の場で非難しているのです。今までのミサ曲とは余りにも違う大胆な演奏は、世間では受け入れ難いものだったのでしょう。今日では、本作品は評論家からの評価は得ているものの、ベートーヴェンの大規模作品としては最も演奏機会の少ない部類に入り、社会派ジャーナリストのマイケル・ムーアは「この作品は、約15年後に書かれた大作『ミサ・ソレムニス』の影に隠れてしまうことも多いが、後期作品には欠けていることもある直截さと情動的内容を有している。」と記し、その存在を高く評価しています。
しかし、その結果はハイドンの思惑とは異なり、依頼主(エステルハージ侯爵)はこの作品を公の場で非難しているのです。今までのミサ曲とは余りにも違う大胆な演奏は、世間では受け入れ難いものだったのでしょう。今日では、本作品は評論家からの評価は得ているものの、ベートーヴェンの大規模作品としては最も演奏機会の少ない部類に入り、社会派ジャーナリストのマイケル・ムーアは「この作品は、約15年後に書かれた大作『ミサ・ソレムニス』の影に隠れてしまうことも多いが、後期作品には欠けていることもある直截さと情動的内容を有している。」と記し、その存在を高く評価しています。 しかし、その頃のベートーヴェンは、音楽への強い情熱から新たな創作活動を進め 、30歳代で「英雄」「運命」「田園」などの中期を代表する名作を次々と発表していくのです。
そして彼が次の「荘厳ミサ」op123まで、長い間ミサ曲を作曲しなかったのは、当時のウィーンでは教会が大きな力を持ち、ミサ曲などの音楽に対し厳格なチェックを行っていたためと考えられます。いわゆる宗教改革の嵐が吹き荒れており、ベートーヴェンが作曲する宗教曲が、当時の教会の考え方とそぐわなかったのが原因の一つとも考えられるのです。古き習慣を守ろうとする教会側と、民衆の側に立つベートーヴェン、これも時代の流れが作り出した運命なのかもしれません。
ベートーヴェンの「荘厳ミサ」、完成するまでに長い時間が過ぎていますが、その時代背景に着目してみます。ベートーヴェンが活躍した18世紀後半から19世紀前半は、ドイツとオーストリアを統合していた神聖ローマ帝国の都ウィーンに多くの音楽家が集まり、古典派に属する作曲家が、多くの交響曲や協奏曲、ピアノ・ソナタ、弦楽四重奏などが作られています。
その中で、ベートーヴェンは、音楽を貴族の世界から市民社会へ解き放した存在であり、古典派からロマン派への橋渡しをしたと言えるでしょう。
 ベートーヴェンがボン大学に入学した19歳(1789年)にフランス革命が勃発し、「自由・平等・博愛」の精神はその後のベートーヴェンに大きな影響を与えています。22歳(1792年)の時には、シラーの詩『歓喜に寄せて』とも出会っているのです。そして同年、ロンドン滞在からボンに立ち寄ったハイドンは、宮廷楽団の演奏で、ベートーヴェン作曲の「皇帝ヨーゼフ2世の死を悼むカンタータ」を聞き、その才能を認め、ウィーンへの留学を勧めたのです。
ベートーヴェンがボン大学に入学した19歳(1789年)にフランス革命が勃発し、「自由・平等・博愛」の精神はその後のベートーヴェンに大きな影響を与えています。22歳(1792年)の時には、シラーの詩『歓喜に寄せて』とも出会っているのです。そして同年、ロンドン滞在からボンに立ち寄ったハイドンは、宮廷楽団の演奏で、ベートーヴェン作曲の「皇帝ヨーゼフ2世の死を悼むカンタータ」を聞き、その才能を認め、ウィーンへの留学を勧めたのです。 ベートーヴェンが難聴であったこともあり、多くの会話やメモが彼の手帳に残されています。そのおかげで、後年の研究者は当時の時代背景や、教会音楽に関する情報を多く得ることが出来ます。
特にベートーヴェンの交友範囲を知るには、重要な資料になっています。
彼は常にメモ帳を持ち歩いており、筆談の記録以外にも多くの内容が書かれていたのです。
ベートーヴェンが活躍した時代はナポレオン戦争の真っただ中で、没落気味だった貴族は戦費の負担や、一族の人達の戦死などが重なっていきます。音楽家への支援どころではなく、ベートーヴェンへの援助は次々と打ち切られ、彼が「市民階級の作曲家(フリーランス)」になったのは、そういった時代背景もありました。 しかし、その中で生涯にわたってベートーヴェンを援助した人が、ルドルフ・フォン・エスターライヒ、「ルドルフ大公」です。在位わずか2年だったハプスブルグ皇帝レオポルト2世の末っ子で、父は音楽をあまり庇護しませんでしたが、ルドルフ大公はベートーヴェンに師事し、自らも演奏・作曲をし、ベートーヴェンとの師弟・パトロンといった関係を超えて生涯の友人となるのです。大公は病弱で、若干43歳で亡くなっていますが、ベートーヴェンは彼の生前たくさんの曲を献呈し、また彼からも献呈されています。
 ピアノの生徒だったルドルフ大公のためでしょうか、ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 Op.97「大公」はヴァイオリンとチェロに負けず劣らず、ピアノが大変活躍する曲となっています。その有名なメロディーは、放送などにも使われることが多く、芸術を愛した大公と、ベートーヴェンの友情の旋律は、現在でも世界中で奏でられているのです。
ピアノの生徒だったルドルフ大公のためでしょうか、ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 Op.97「大公」はヴァイオリンとチェロに負けず劣らず、ピアノが大変活躍する曲となっています。その有名なメロディーは、放送などにも使われることが多く、芸術を愛した大公と、ベートーヴェンの友情の旋律は、現在でも世界中で奏でられているのです。ベートーヴェンに纏わる不思議な「2」の数字、12歳の時に最初の作品「ドレスラーの行進曲にる9つの変奏曲」、22歳でハイドンに弟子入り、同年に父親を亡くしています。32歳でハイリゲンシュタット遺書を、42歳で「不滅の恋人への手紙」を書いており、同年にゲーテと出会っています。52歳で新作の交響曲(後の第九)の依頼をロンドンから受けています。
ベートーヴェンの事ですから、作曲の依頼を受ける前から次の準備に取り掛かっています。その頃作曲された作品の中には、イギリスに関係するものが多くあります。しかし、体調がすぐれなかった時期と重なり、彼のイギリス行は実現しませんでしたが、教会との関係についても無条件で受け入れられる関係ではなかったようです。「荘厳ミサ」の初演がウィーンではなく、サンクト・ペテルブルクで「オラトリオ」として演奏(1824年4月7日)されたのも、検閲から逃れるためだったと推測できます。また想い人についても諸説あり、いまだにわからない部分も多く、彼の死後に発見された手紙やメモなどからも今後どんなことが判明するかが楽しみです。
 ワイン好きであったが為に、死因説が鉛入りのワインを飲みすぎたと言われていますが、これも残された遺髪から通常の40~50倍の鉛が発見されたからで、ワインが原因と特定されたわけではありません。何らかの理由により、体内に鉛が多く取り込まれていたのなら、難聴を直すために弟から入手した薬の成分が原因であったのかもしれません。
ワイン好きであったが為に、死因説が鉛入りのワインを飲みすぎたと言われていますが、これも残された遺髪から通常の40~50倍の鉛が発見されたからで、ワインが原因と特定されたわけではありません。何らかの理由により、体内に鉛が多く取り込まれていたのなら、難聴を直すために弟から入手した薬の成分が原因であったのかもしれません。この遺髪は現在、米国カリフォルニアのサンノゼ州立大学内にあるベートーヴェン研究センターに寄贈されて他の貴重なコレクションとともに展示されています。
今回、ミサ・ソレムニスとベートーヴェンについて調べてみましたが、波乱万丈の人生、ますます謎が深まりました。 【 完 】